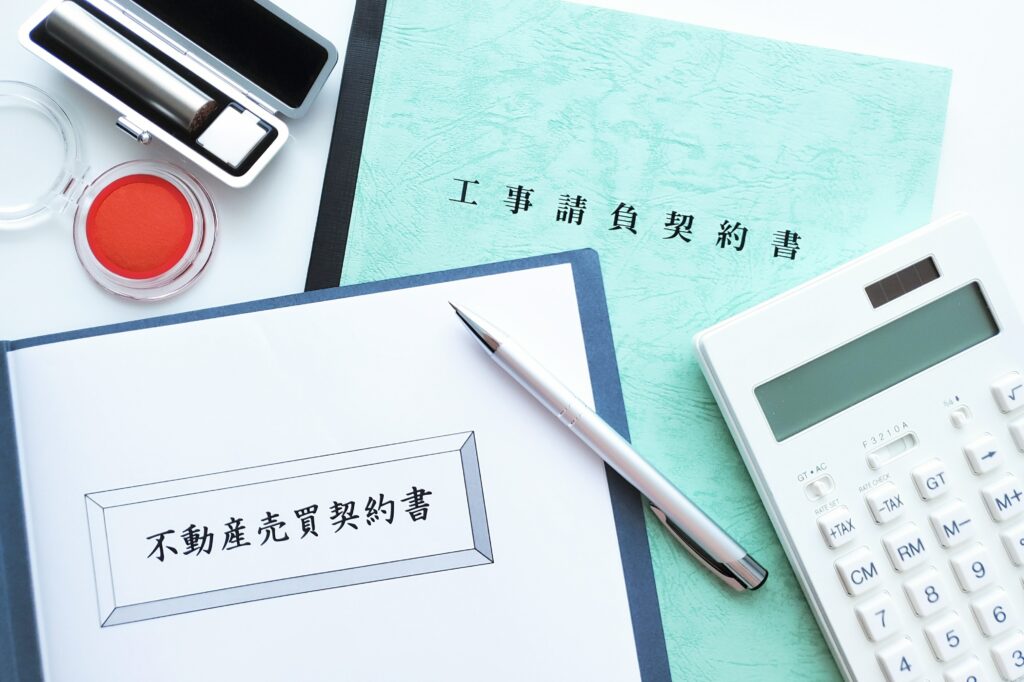
特有の表現
(1)契約書の中では、契約当事者を「甲」「乙」「丙」といった表記で書き表すことが多くあります。通常は、甲・乙・丙くらいまでが多いと思いますが、甲・乙・丙の後は「丁」「戊」「己」「庚」「辛」「壬」「癸」と10個まで続いていきます。漢字1文字だと記載間違いや、読み間違いも生じやすいので、あえて略さずに、賃貸借契約の賃貸人を「貸主」、賃借人を「借主」などの表記で記載したり、ライセンス契約においてライセンスを提供する側を「ライセンサー」、ライセンスを受ける側を「ライセンシー」と表記する場合もあります。決まったルールはないので、契約当事者が明確で、統一して記載されていれば問題はありません。
(2)条・項・号・章番号をつける場合には、法令を記載する場合のルールに準じて、「条」「項」「号」の順番で付していきます。数十条や百条に及ぶ契約のような場合には「条」の前に「章」を設けることもあります。「条」については「第1条」「第2条」「第3条」……と表記していきます。「項」については「1」「2」「3」……と記載していく例が多く、「号」については「①」「②」「③」……と記載していく例が多いです。よく「項」なのに「号」の番号が付されていたり、「号」なのに「項」の番号が付されていたりする契約書をみることがありますが、同じ契約書の中では、しっかりとルール決めをして、そのルールに従って「条」「項」「号」を記載していくことが必要です。
(3)柱書というのは、条文の中に「号」とよばれる箇条書きで項目を列挙した記述がある場合の同条項の「号」以外の部分のことです。
第○条(期限の利益の喪失)
乙に、以下の各号に規定する事情が生じた場合には、乙は甲からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、直ちに、残債務全額を一括して支払わなければならない。
①乙が個別契約に基づく本件商品の代金の支払いを行わないとき
②乙が振り出し、引受、又は裏書した約束手形・為替手形・小切手が不渡りになったとき
③乙が銀行取引停止処分を受けたとき
④乙に対して、競売、差押え、仮差押え、又は仮処分の申立てがなされたとき
⑤乙が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを行い、又はこれらの申立てを受けたとき
⑥乙の信用及び資力が悪化したと甲が認めるとき⑦そのほか、本契約に定める各条項に違反したとき
(4)但書というのは、「但し」や「ただし」の語を書き出しにして、前文や本文の内容などについての説明・条件・例外などを書き添えた文のことをいいます。
第○条(有効期間)本契約の有効期間は、本契約締結日から令和○年○月○日までとする。ただし期間満了の1か月前までに甲又は乙のいずれからも終了の意思表示が無い場合には、本契約は自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(5)並びに・及び2つ以上のものを並列で並べるときに「及び」「並びに」という接続詞を使用します。大きいものを並べる場合には「並びに」を用い、小さいものを並べる場合には「及び」を使います。
(6)又は・若しくは2つ以上のものを選択的に並べるときに「又は」「若しくは」という接続詞を使用します。大きいものを並べる場合には「又は」を用い、小さいものを並べる場合には「若しくは」を使います。
(7)場合・とき・時契約書の条項の中で「場合」「とき」「時」は混同しがちな法律用語です。理解せずに使用されている契約書を目にする機会も多いのですが、一般的には以下のように整理できますので、ご確認ください。
まず「時」ですが、「時」は時間的な一瞬を指す言葉です。まさにその瞬間、その時点をピンポイントで指します。たとえば、会社法215条4項に「4前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる」と規定されていますが、これは時点を示しています。
次に、「場合」と「とき」は、いずれも仮定的な条件を定める際に使用します。どちらを使用しても問題ありません。ただ、「場合」のほうが最初の仮定的な条件を意味しますので、仮定的な条件が重なる場合には、最初に「場合」を用いて、次に「とき」を使うと考えてください。たとえば、会社法247条には「場合」と「とき」が出てきますが、最初の段階の仮定の条件に「場合」を用いて、次の段階の仮定の条件に「とき」を用いています。
(8)することができる・することができない条文の末尾に着目すると、そこにも紛らわしい表現がでてきます。順に確認していきます。「~することができる」ですが、よく2つの場面で使われます。1つ目は、一定の行為をするかしないかの裁量権が付与されている場合です。してもしなくてもよいし、どっちも選択することができます。もう1つは、一定の行為をする権利または能力が浮揚された状態を示す場合です。いずれも英単語に置き換えると「CAN」が近い意味になります。そして、一定の行為をする権利または能力がないことを示す場合には「~することはできない」と規定することになります。
(9)しなければならない・するものとするよく見かけるのは「~しなければならない」「~するものとする」という語尾です。いずれも作為義務が課せられている場合を示します。どちらかというと「~しなければならない」に比べると、「~するものとする」の方が義務の程度は弱いニュアンスがありますが、いずれも義務であることに違いはありません。ただ「~するものとする」とした場合には、取扱いの原則や方針を示すだけの意味の場合も含まれますので、解釈に曖昧な点が残ります。そのため、誤解を招きかねない場面では「~するものとする」は用いないほうが無難です。
(10)してはならない・してはならないものとする「~してはならない」「~してはならないものとする」という語尾も見かけますが、こちらはいずれも不作為義務が課せられている場合を示します。「~してはならないものとする」にも「~するものとする」と同様に曖昧な点が残ることと、くどいし、わかりづらいので用いないほうが無難です。ただし、不作為義務として少し弱めの表現にし、念のため確認するという使い方もすることがあります。
(11)努めなければならない・努めるものとする「~努めなければならない」「~努めるものとする」という語尾も見かけます。いずれも努力義務なので、それを怠ったとしても直ちに債務不履行責任が発生しうるものではありません。これも上記と同様で、やや弱めの表現にして駆け引きして使うこともあります。
(12)みなす・推定する「~とみなす」「~と推定する」という語尾も注意が必要です。両者の違いは反証の余地を残すか否かです。「みなす」の場合には反証の余地を残さないのに対し、「推定する」の場合には反証の余地を残します。たとえば、「オレンジ色の電車はJR中央線とみなす」とした場合には、反証の余地はなく、すべてJR中央線として取り扱われることになりますが、「オレンジ色の電車はJR中央線と推定する」とした場合には、オレンジ色の電車がJR武蔵野線だったときには、覆る可能性があります。
(13)適用する・準用する法令や条項について「適用する」としている場合と、「準用する」としている場合があります。それぞれ違いがありますので、注意が必要です。すなわち、「~を適用する」の場合には、「~」の規定を、類似する他の場面にそのままあてはめて使用することになります。他方で、「~を準用する」の場合には「~」の規定を類似する他の場面で必要な修正をしたうえで使用することになります。
(14)直ちに・速やかに・遅滞なく時間的な間隔を示す言葉として「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」という言葉があります。早い順に示すと「直ちに>速やかに>遅滞なく」となります。読み手の感覚によって解釈の幅がでてしまうので、あえてぼやかしておく必要がない場合には「〇日以内に」「〇営業日以内」という形で明確にしておいたほうがよいと思います。
(15)者・物・もの単に「もの」と記載されている場合には注意が必要です。「もの」という音で示される意味合いには3つがありますので、区別が必要です。
(16)その他・その他の「その他」「その他の」の使用方法にも区別が必要です。「その他」は並列関係になります。すなわち、「A、B、C、その他D」とした場合に「A」「B」「C」「D」は並列です。他方で、「その他の」は包含関係になります。「A、B、C、その他のD」となった場合に「A」「B」「C」は「D」に含まれることになります。
(17)から・より「AからBに通知する」という場合に、「から」は起点として用いられることになります。「AがBに通知する」という意味です。この場合に「AよりBに通知する」と記載される場合がありますが、これは正確ではありません。「より」は「AよりBの方が素晴らしい」といった形で、起点ではなく、比較の意味合いで用いられます。
18)通知する・書面で通知する・事前に通知する・事前に書面で通知する契約書では微妙なニュアンスを正確に記載する必要があります。たとえば、通知に関して、単に「通知する」とした場合には、事前でも事後でもよいから通知さえすればよいことになります。「書面で通知する」とした場合には、方法は書面で行う必要がありますが、時期は事前でも事後でもよいことになります。「事前に通知する」とした場合には、事前に通知すれば、口頭でも書面でも方法は何でもよいことになります。「事前に通知する」だけでは、「言った」「言わない」の問題が残るため、「事前に書面で通知する」という形で、時期と方法を特定しておいたほうが、疑義を生じないということになります。これと同様のことは「承諾を得たうえで」という文言の適用場面でも生じますので、同様の観点から確認して疑義が残らないようにしてください。
(19)協議する・協議したうえで決定する重要な事柄を決定せずに「協議する」のままにしている条項は、あまり望ましくありません。たとえば「契約期間終了後の更新の有無は、AB協議する」という規定だと、いつまでに協議するのか、または協議した結果、話がまとまらなかった場合にはどうなるのかが不明です。何となく積み残しにしてしまうと、後日のトラブルや紛争の種になります。決めるべきことは、明確に定めておくべきです。
「契約期間終了後の更新の有無については、本契約終了日の1か月前までにABが協議して決定する。協議が調わない場合には、本契約は延長されないものとする」とか「契約期間終了後の更新の有無については、本契約終了日の1か月前までに甲乙が協議して決定する。協議が調わない場合には、本契約は自動的に1年間だけ延長される」といった形で、その後のことを明確にすべきです。
以上のように、法的な観点からの言葉選びの重要性もさることながら。契約書は法的な効力を持つ文書であり、裁判所において有効性が問われることもあります。そのため、法的な観点から見て適切な文言や条文を使用する必要があります。契約書作成には専門の知識が必要となる場合もありますので、法律の専門家への相談も検討してください。